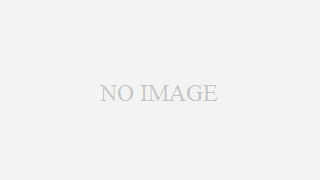 進化論批判
進化論批判 聖書と進化論の限界Ⅰ―第7回 DNA・エピジェネティクス・複雑系科学が示す進化論の限界
1. はじめに:21世紀の生物学は進化論の限界を暴きつつあるダーウィンが進化論を提唱した19世紀、生命の仕組みはほとんど知られていませんでした。細胞は単純な構造と思われ、遺伝の仕組みも解明されていなかったため、「小さな変化が蓄積すれば新しい...
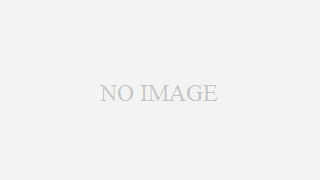 進化論批判
進化論批判 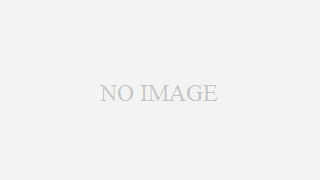 進化論批判
進化論批判 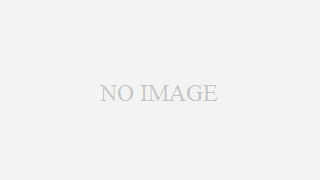 進化論批判
進化論批判 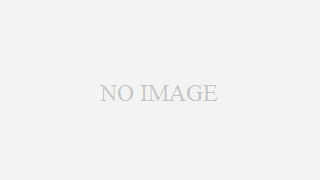 進化論批判
進化論批判 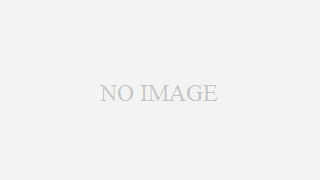 進化論批判
進化論批判 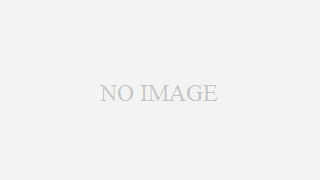 進化論批判
進化論批判 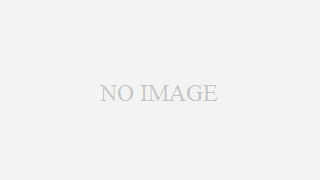 進化論批判
進化論批判 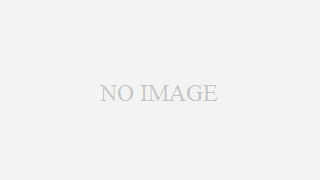 進化論批判
進化論批判 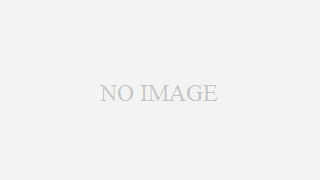 共産主義批判
共産主義批判 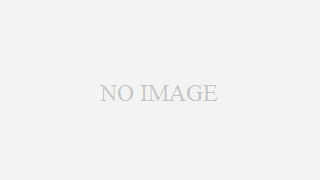 共産主義批判
共産主義批判